![]()
新潟にはかつて、”堀”が存在したそうです。
管理人は、見たことがありません。
堀があった地域は、
現在も、地名に”堀”がついているところがあります。
西堀、東堀、一番堀通。
堀がついていないところでは、
早川町、蔵所堀などです。
現在、残念ながら、すべて埋め立てられています。
新潟では、堀のほかに、異人池、沼など、多くが埋め立てられたと聞いています。
昔の新潟のシンボルだった堀。
その歴史や、今残る風景などをお話していきます。
「堀と柳の都」と言われた新潟。
明治の半ば、市内を流れる堀は30を超え、そこに架かる橋は100本をはるかに超えていたそうです。
また、堀の両側には柳が植えられ、
信濃川から米や薪などを積んだ船がのどかに往来していたそうが、
かつての新潟市街を縦横に結んでいた堀と、
そこにかけられた多くの橋は、
1960年代にすべて姿を消したそうです。
しかし、東堀通、古町通、西堀通、の九番町と十番町の間を
東西に横切っていた「広小路堀(四番堀)は、
今は水こそ流れていませんが、
当時の姿を比較的とどめているのではないか、
と語る方もいらっしゃいます。

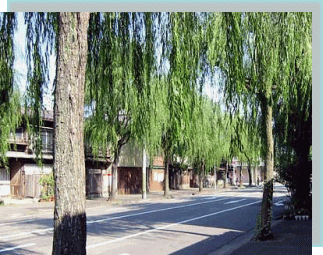
柳が素敵ですね
下の写真は、「月見橋」。
広小路堀が東堀と交差するあたりで、この月見橋を渡って人が自由に往来できるようになっていたそうです。
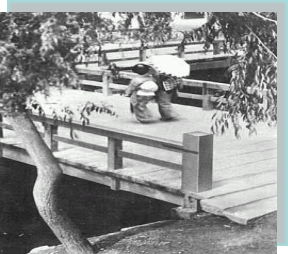
広小路堀には、この月見橋のほか、「寝覚橋」「霞橋」「空見橋」などの雅名が連なっていたといいます。
かつての堀の姿は、美しい柳並木の助けを借りて想像するしかないですね。
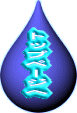 |
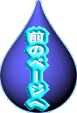 |
|---|